
2023年7月に打ち上げられたユークリッド宇宙望遠鏡。そのユークリッド望遠鏡の早期リリース観測の一環で撮影された画像が公開されました。上の画像は公開された5点のうちの1点で、星形成領域M78が映っています。
画像の中央にある明るい領域がM78です。M78はオリオン座の方向、1300光年の距離にあります。
ユークリッド望遠鏡は赤外線でM78を撮影し、新たに形成された恒星や惑星サイズの天体を明らかにしました。可視光で見ると、それらの天体はガスと塵の暗い雲によって隠されてしまいますが、赤外線で観測したことでガス雲の内部を探索することができました。
ユークリッド望遠鏡は、この視野内だけでも30万を超える数の新たな天体を明らかにしました。そのデータをもとに研究者は、恒星と、恒星質量に満たない軽い天体との間の比率などを研究しています。これは、星の種族がどのように形成され、どのように時間とともに変化するのかを理解するための鍵となります。褐色矮星や自由浮遊惑星などの恒星質量に満たない天体はまた、ダークマター(暗黒物質)の候補の1つでもあります。
画像の上端付近には、もう1つの明るい星雲NGC 2071も見えています。

こちらはM78のクローズアップ。
ユークリッド望遠鏡にはVIS(可視光カメラ)とNISP(近赤外線分光計および測光計)という2つの観測機器が搭載されています。これらのカメラを使うと、4つの異なる波長範囲で観測を行うことができます。
冒頭の画像は、0.7μm、1.1μm、1.7μmの波長で得られた画像を青、緑、赤に割り当てて色合成したものです。M78の画像では、高温の星は青白い色合い、励起された水素ガスは青、塵や分子ガスが豊富な領域は赤い色合いとなっています。
(参考記事)オリオン座の反射星雲M78(地上望遠鏡が可視光で撮影したM78の画像を掲載しています)
6年間で全天の3分の1の領域を観測する
ユークリッド望遠鏡は、太陽・地球系の第2ラグランジュ点(L2)を周回する軌道から観測を行っています。L2は、地球からみて太陽の反対側、約150万km離れたところにあります。全天の3分の1の領域について、100億光年先までの銀河の形状や位置、距離などを測定し、宇宙の3Dマップを作成することが目的です。それにより、ダークエネルギー(暗黒エネルギー)やダークマターの解明などを目指しています。
(参考記事)ユークリッド宇宙望遠鏡 銀河の精密な3Dマップを作り宇宙の「暗黒」の解明を目指す
2024年5月23日に公開された今回の5点の画像は、同日公開されたミッションの最初の科学データおよび、今後発表される10件の科学論文に伴うものです。データはわずか24時間の観測から得られたものですが、可視光で1100万以上、赤外線でさらに500万以上の天体が明らかになったとのことです。ユークリッド望遠鏡のメインミッションは6年間が予定されており、今後の成果が大いに期待されます。
今回公開された他の画像については、アストロピクスで順次紹介していく予定です。
(参考記事)
ユークリッド宇宙望遠鏡がとらえた銀河団Abell 2390
ユークリッド宇宙望遠鏡がとらえた渦巻銀河NGC 6744
ユークリッド宇宙望遠鏡がとらえた「かじき座銀河群」
Image Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi


 大宇宙 写真集500【改訂新版】
大宇宙 写真集500【改訂新版】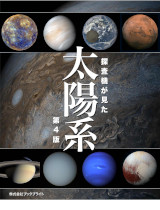 探査機が見た太陽系【第4版】
探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】
