
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、オリオン大星雲(M42)の中心部をとらえた画像が公開されました。この画像はウェッブ望遠鏡のNIRCam(近赤外線カメラ)の短波長チャンネルで撮影されたものです。
オリオン星雲は、地球から1300光年の距離に位置しています。オリオン星雲の中心部には、「トラペジウム」と呼ばれる4つの高温の星があります。画像はトラペジウム周辺の星形成領域をとらえたもので、画像の中央sにトラペジウムが映っています。
この星形成領域は、誕生してからわずか100万年ほどしか経過していません。そこには太陽質量の10分の1未満から40倍の範囲にわたる、さまざまな質量の数千の新たな星が含まれています。また質量が小さく中心で核融合反応が起きていない褐色矮星や、惑星質量の天体も存在しています。ウェッブ望遠鏡のデータから、恒星を周回していない「自由浮遊惑星」が数百個あることも明らかになりました。
トラペジウムの右上には「オリオンKL(クラインマン・ロウ星雲)」と呼ばれる星雲が赤く見えています。一方、トラペジウムの左下側には、「オリオン・バー」と呼ばれる、トラペジウムからの紫外線によってガスが電離されている境界面が斜めに走っています。

こちらはオリオンKLの一部のクローズアップです。オリオンKLはおそらく、500〜1000年ほど前に2つの若い星が衝突し爆発して形成されたとみられます。なお冒頭の画像のオリジナルは21,000×14,351ピクセルもある巨大なもので、一部をクローズアップしたこの画像も非常に鮮明です。
NIRCamの長波長チャンネルの画像

この画像は、冒頭の画像と同じ範囲をNIRCamの長波長チャンネルで撮影したものです。トラペジウム周辺は空洞になっており、紫色で見えている電離ガスで満たされています。その周囲には、赤や茶色、緑に見えている塵や分子ガスが混在しています。冒頭の短波長の画像と比べると、オリオン・バーがくっきりと見えています。

Image Credit: NASA, ESA, CSA / Science leads and image processing: M. McCaughrean, S. Pearson, CC BY-SA 3.0 IGO
(参照)ESA


 大宇宙 写真集500【改訂新版】
大宇宙 写真集500【改訂新版】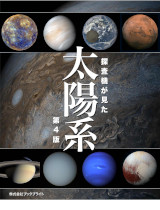 探査機が見た太陽系【第4版】
探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】
