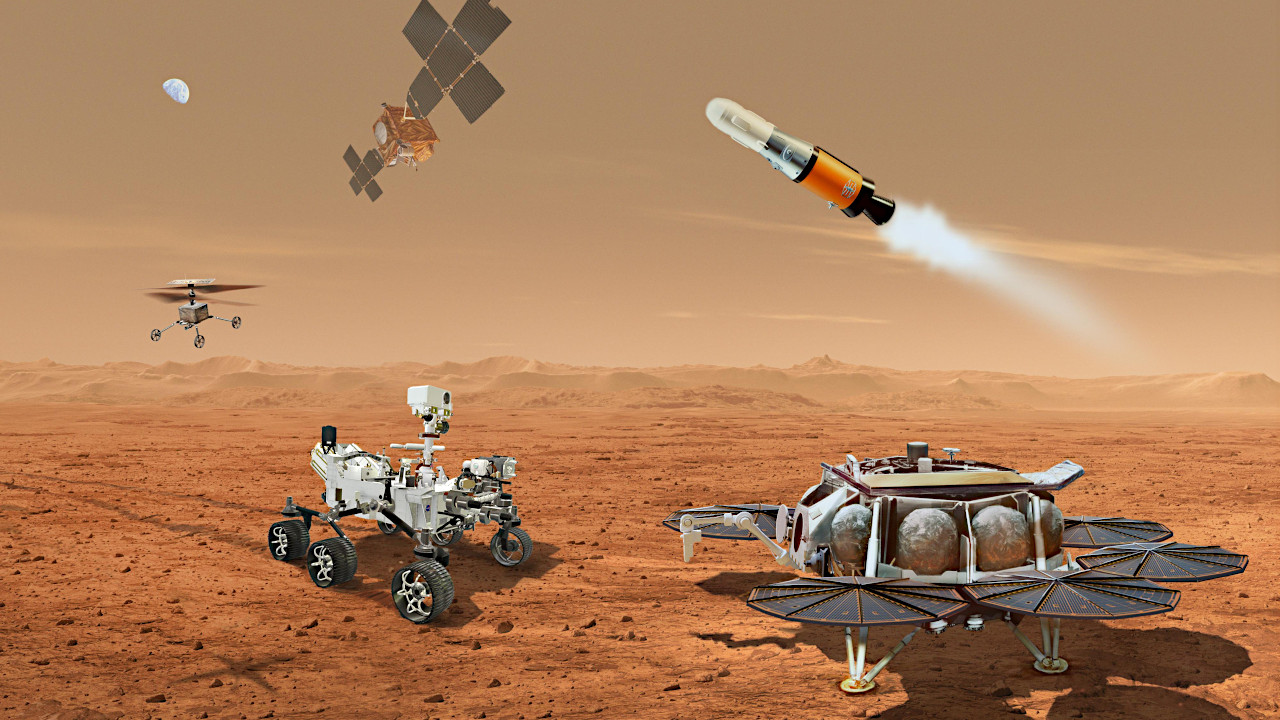 宇宙開発
宇宙開発 衝撃のNASA予算案 惑星探査ミッションはどうなる?
有人での月面着陸を目指すアルテミス計画の見直しなど、NASA(アメリカ航空宇宙局)の予算案が大きな話題となっています。今回の記事では、公表された資料をもとに、N...
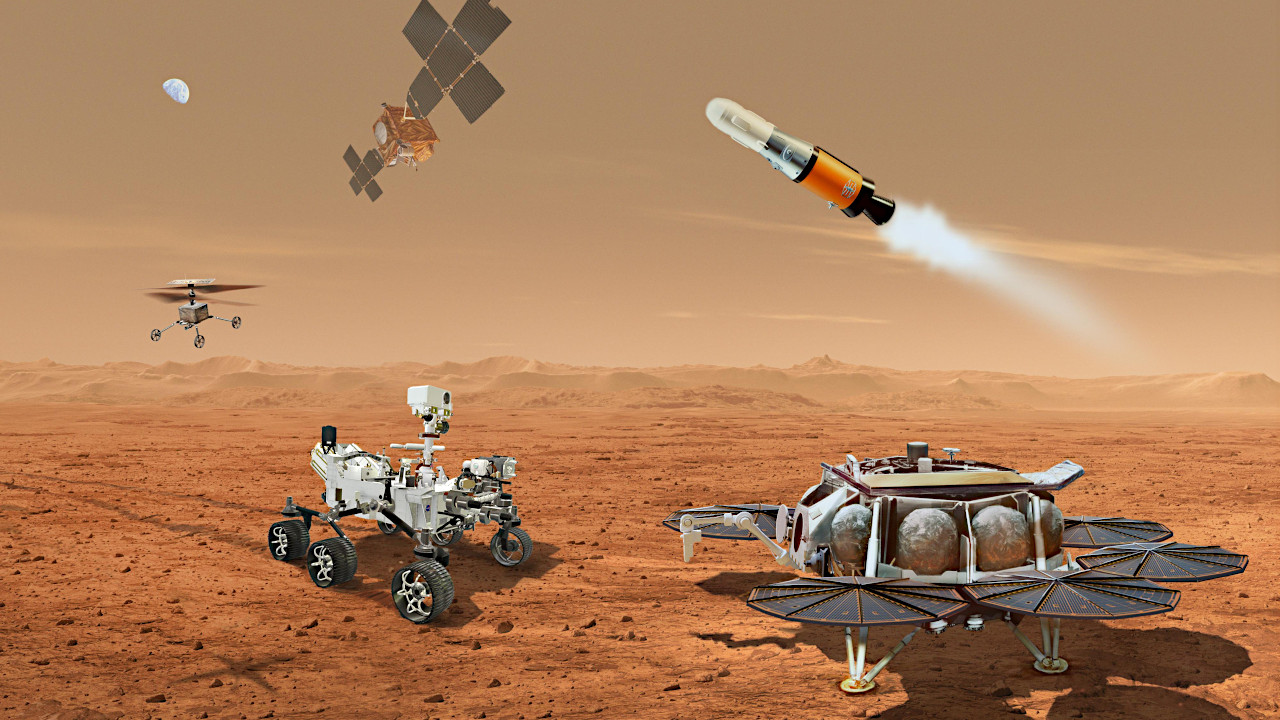 宇宙開発
宇宙開発 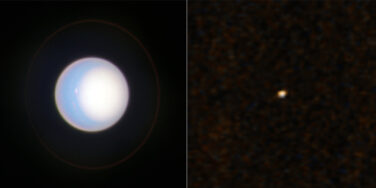 天王星
天王星 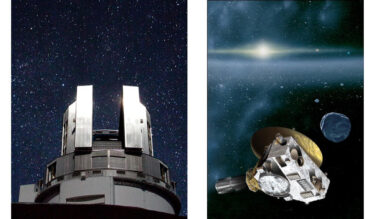 太陽系
太陽系  準惑星
準惑星 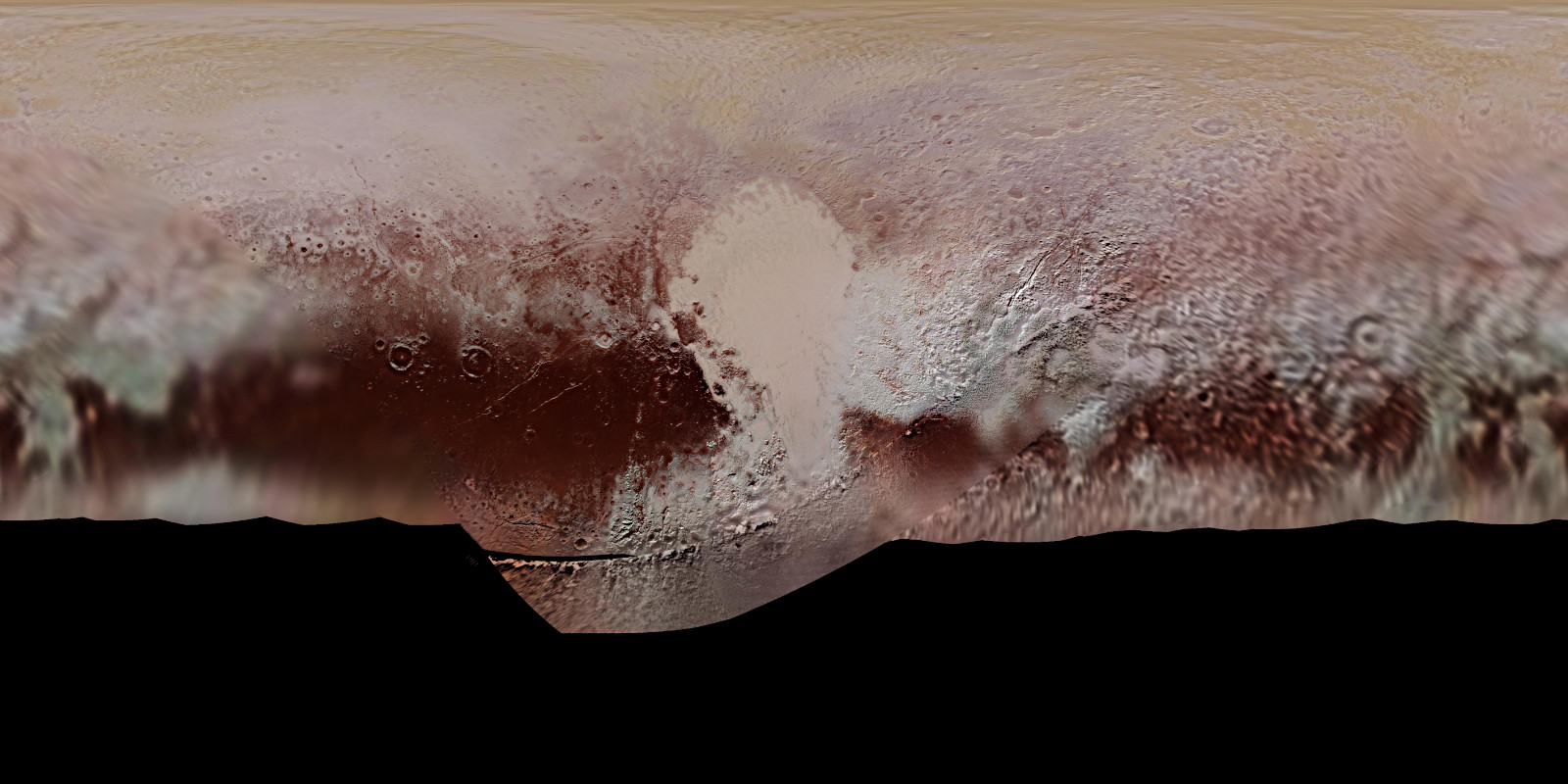 準惑星
準惑星 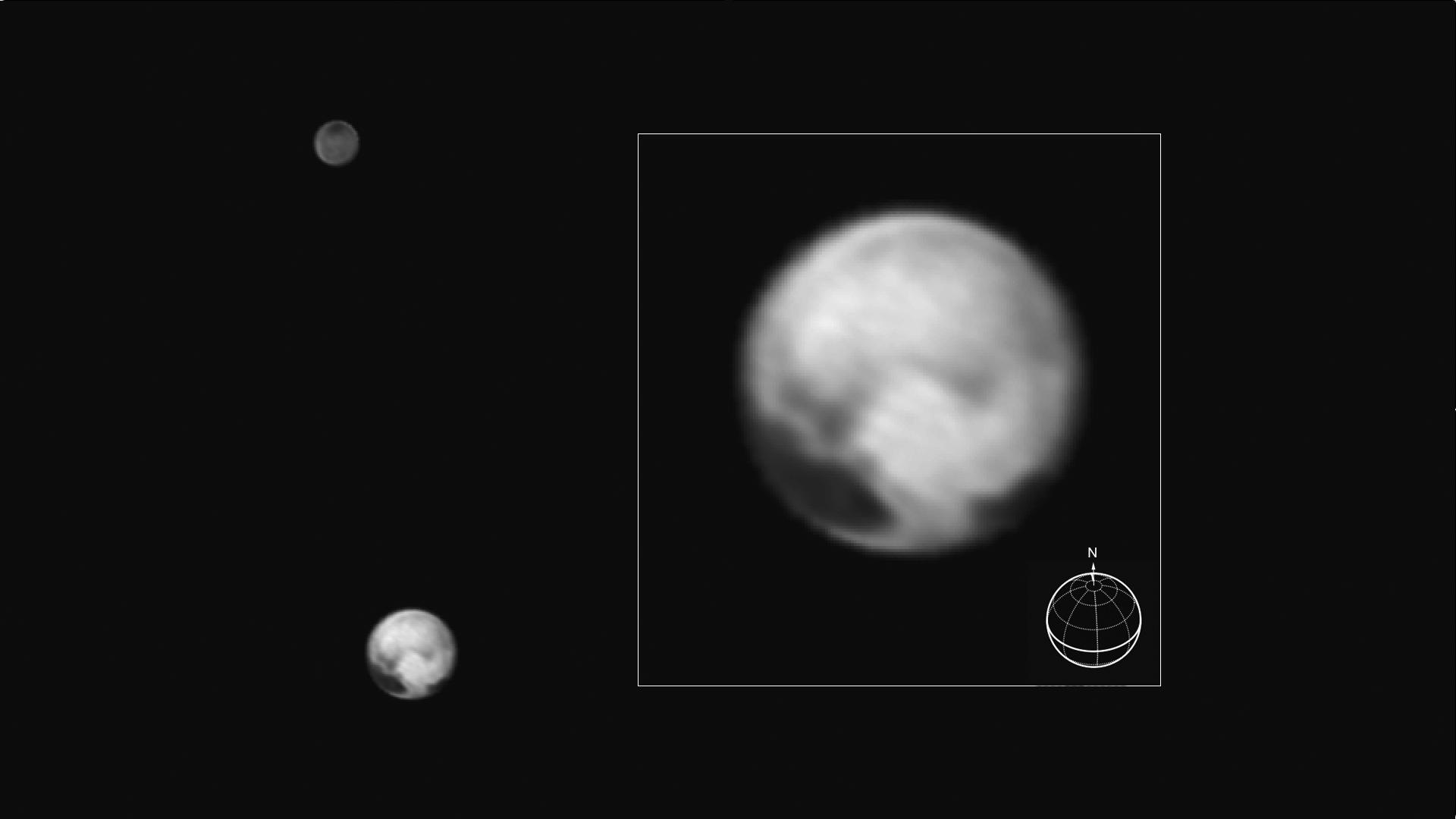 準惑星
準惑星 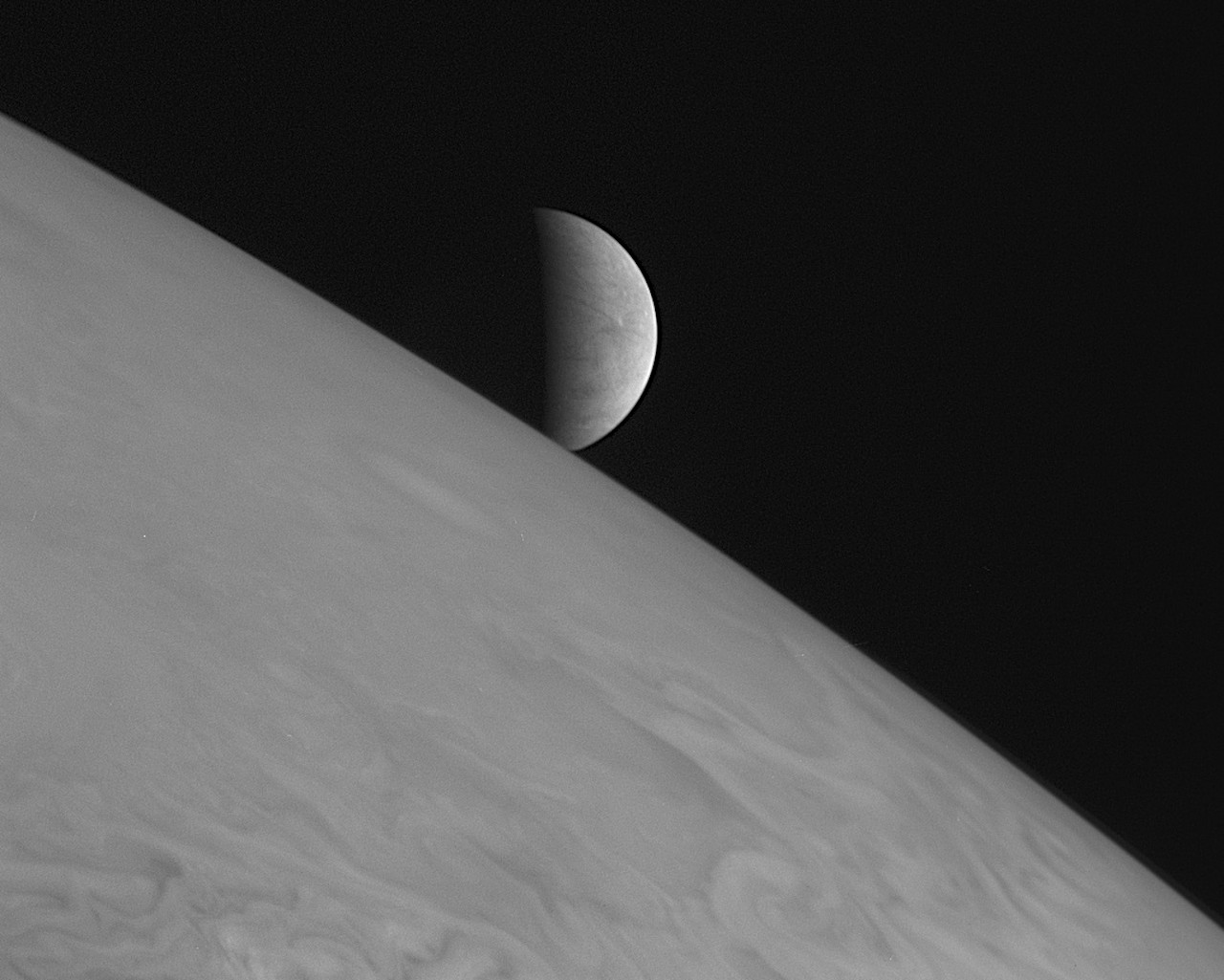 木星
木星 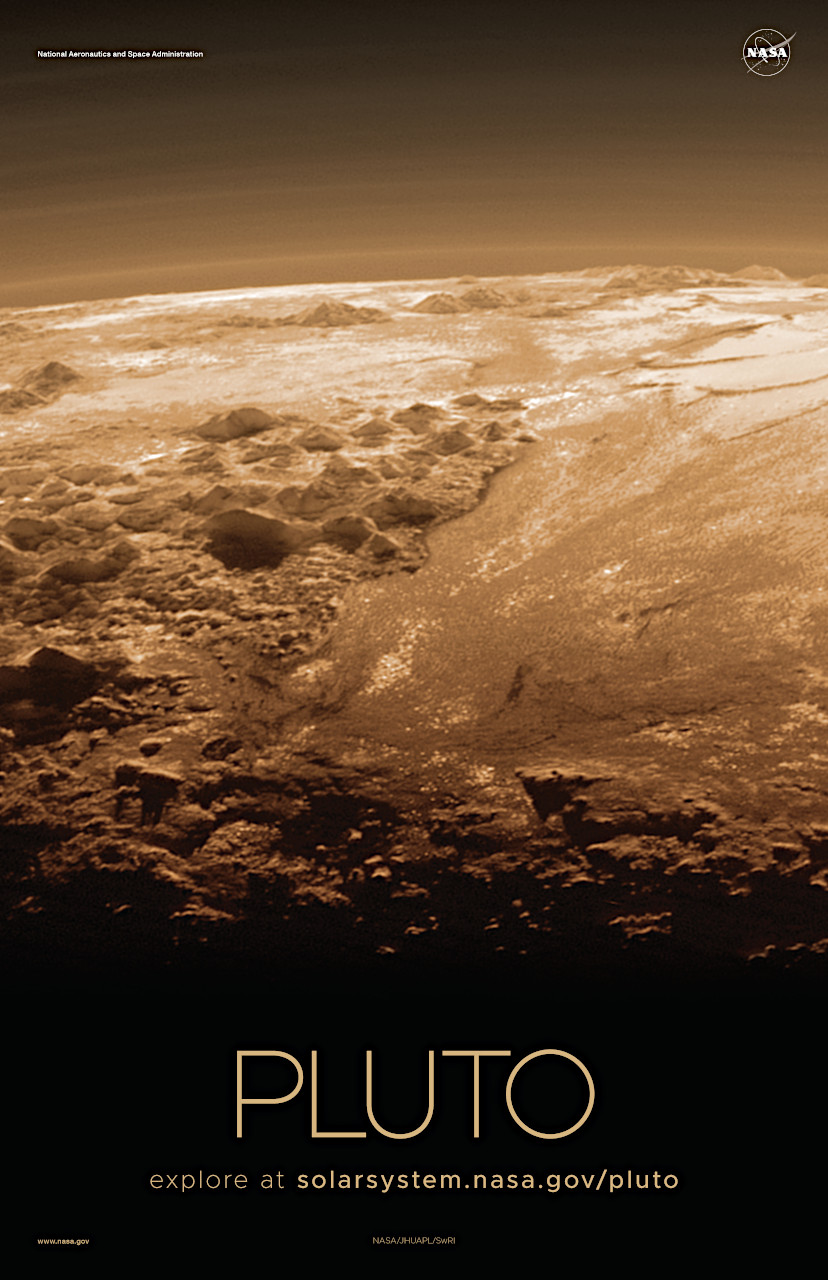 準惑星
準惑星 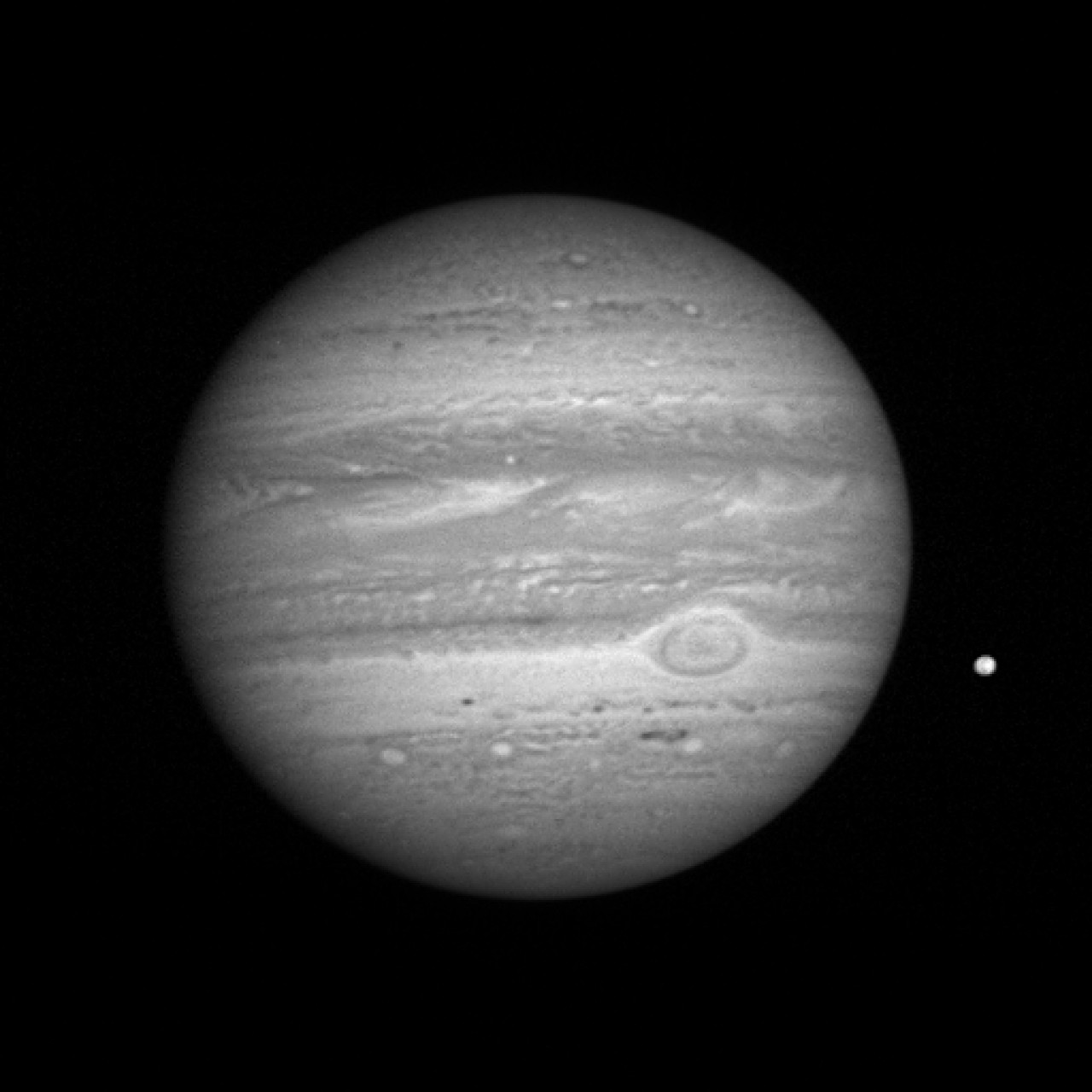 木星
木星  準惑星
準惑星  準惑星
準惑星 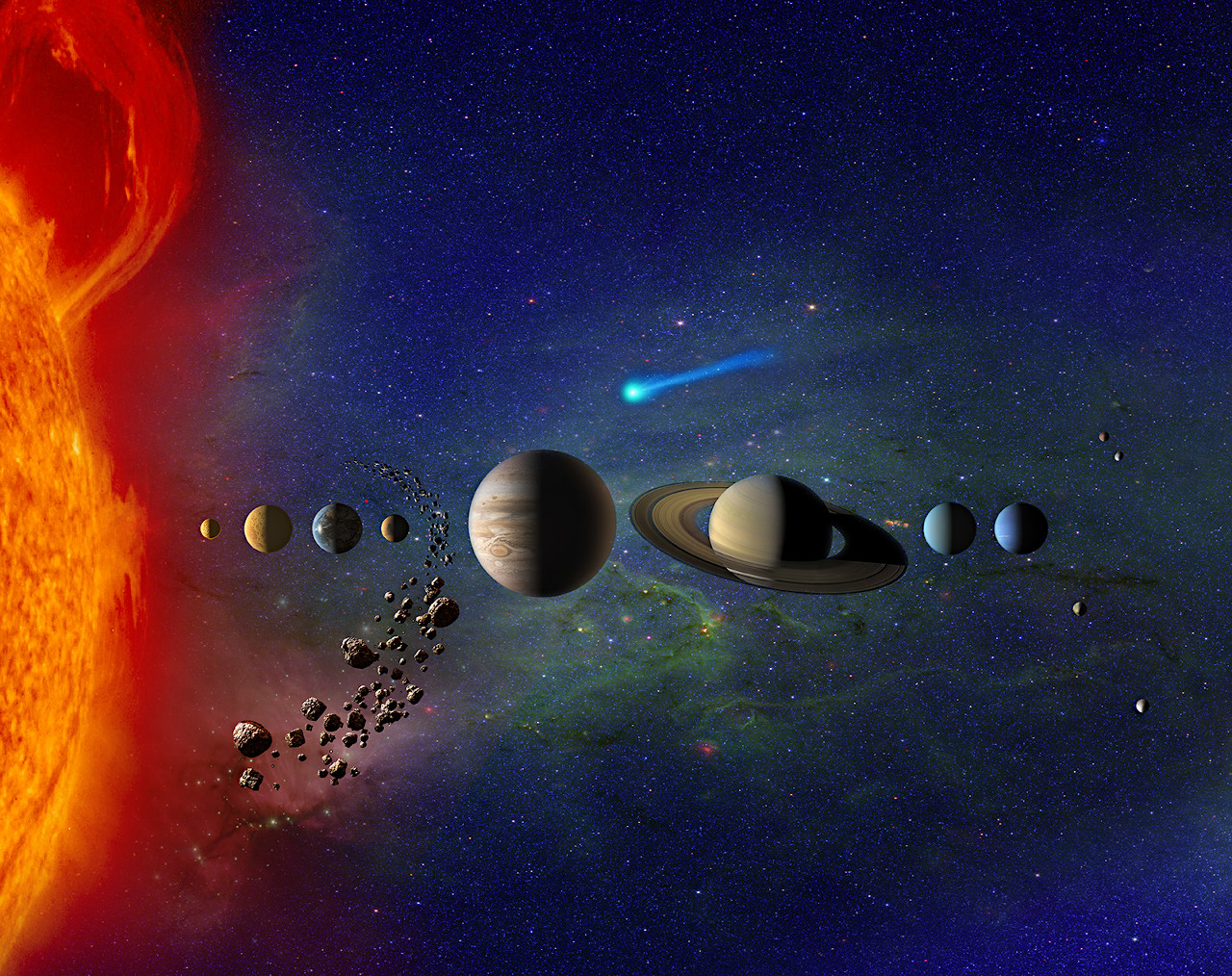 太陽系
太陽系