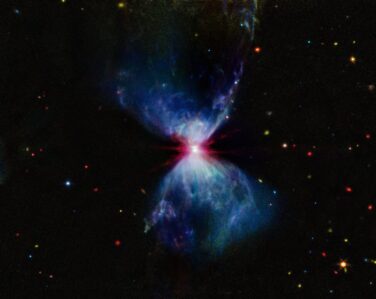 星雲
星雲 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が原始星を包み込む星雲をとらえた
この画像はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影したもので、原始星を取り囲む分子雲「L1527」が映っています。ウェッブ望遠鏡のMIRI(中間赤外線装置)で撮影さ...
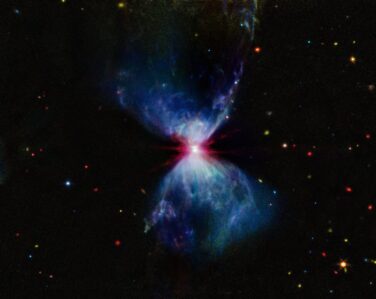 星雲
星雲 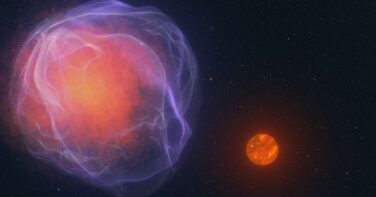 星・星雲・星団
星・星雲・星団  星・星雲・星団
星・星雲・星団 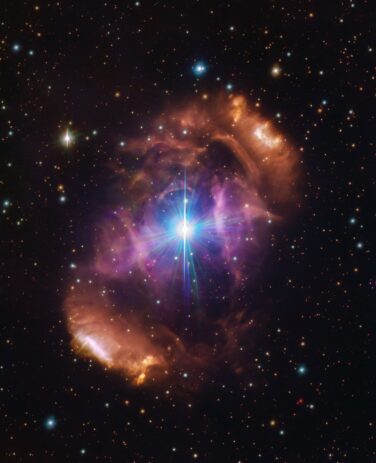 星雲
星雲  超大質量ブラックホール
超大質量ブラックホール  星・星雲・星団
星・星雲・星団 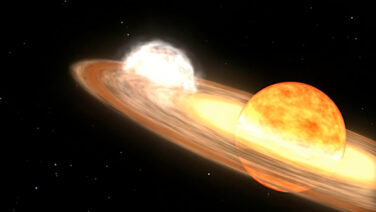 星・星雲・星団
星・星雲・星団 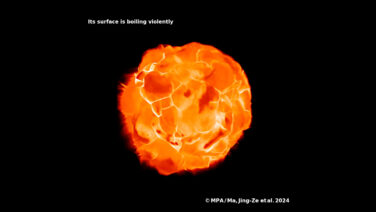 星・星雲・星団
星・星雲・星団 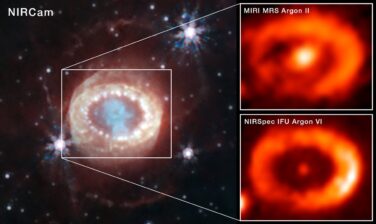 超新星
超新星  星・星雲・星団
星・星雲・星団 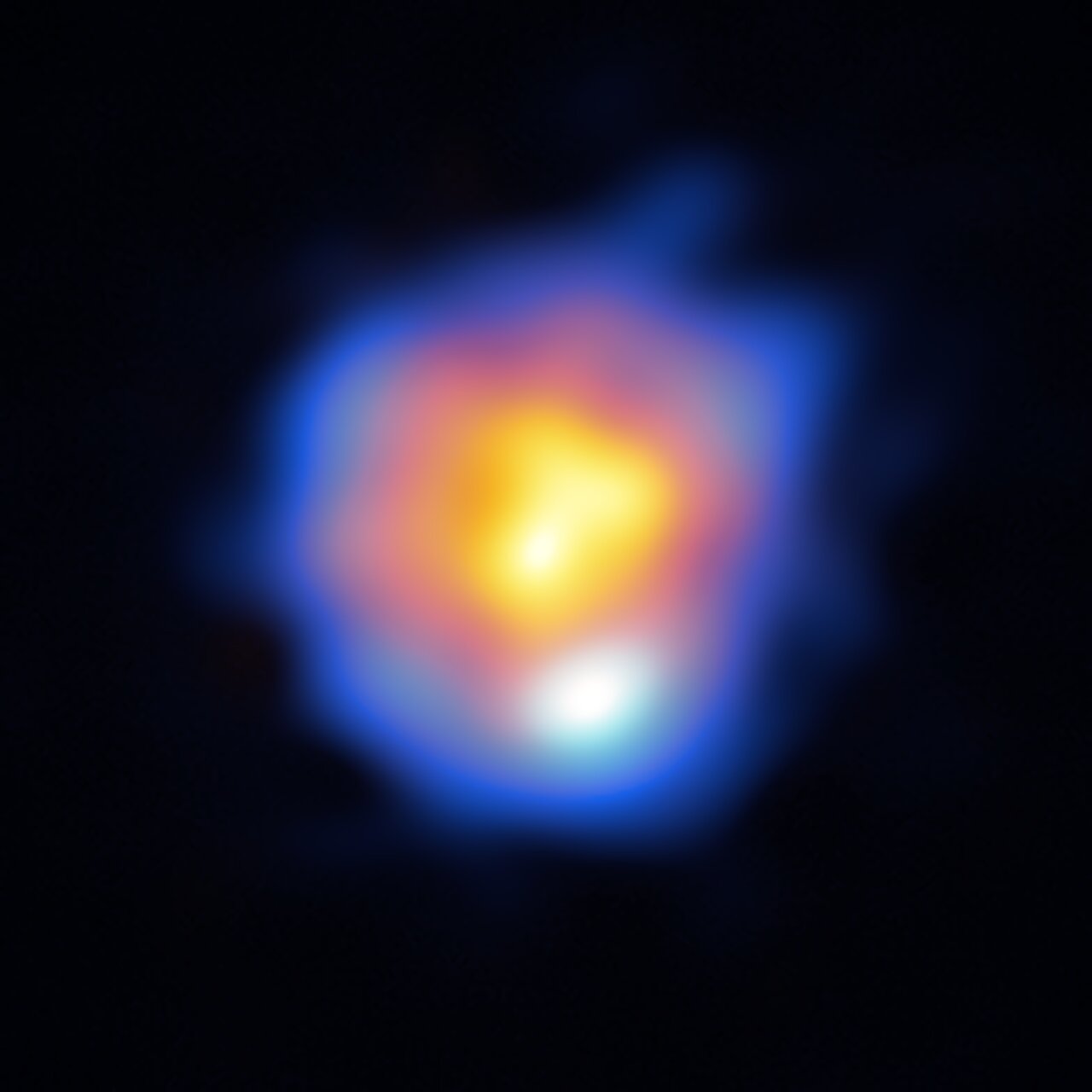 星・星雲・星団
星・星雲・星団 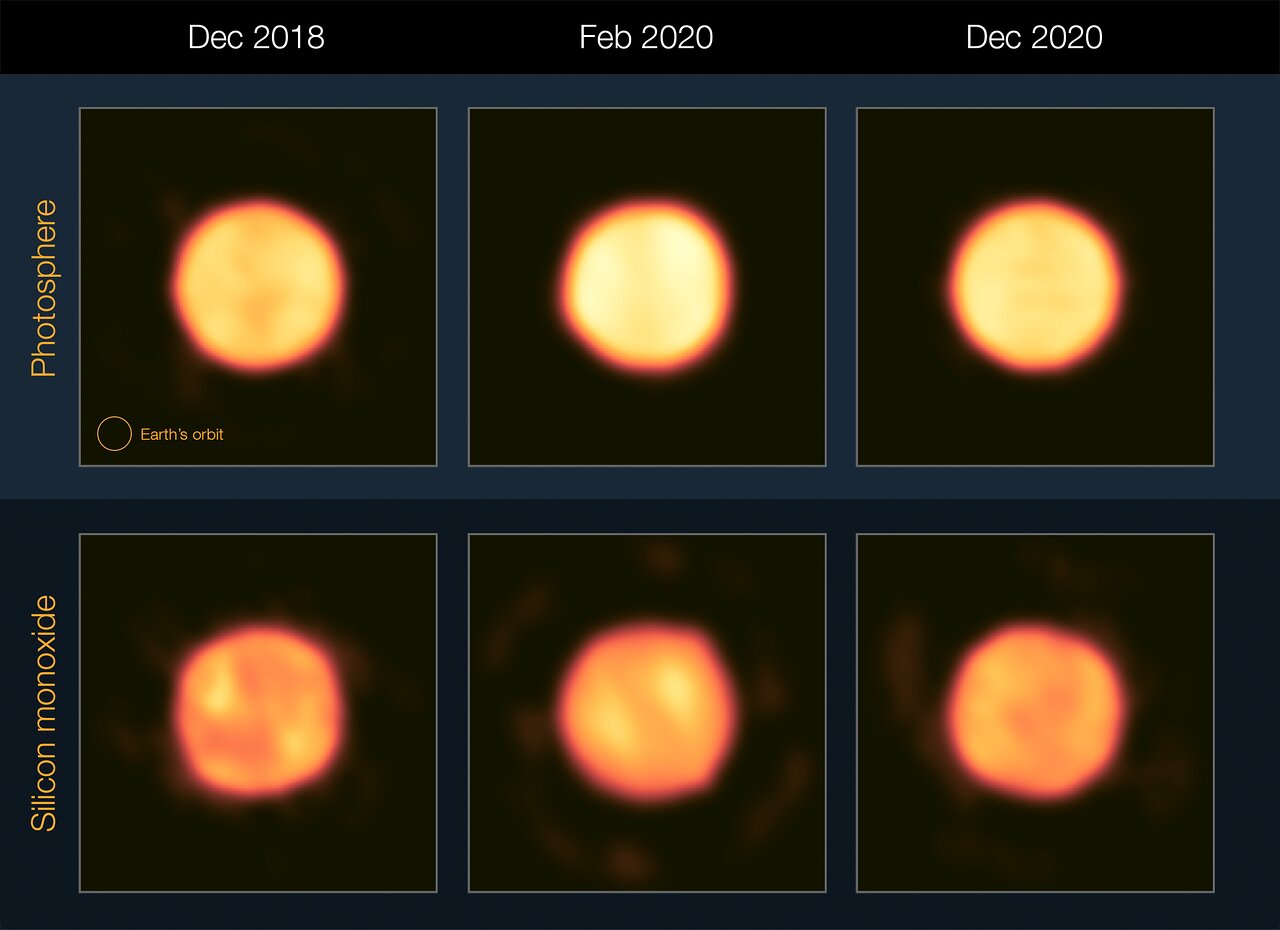 星・星雲・星団
星・星雲・星団